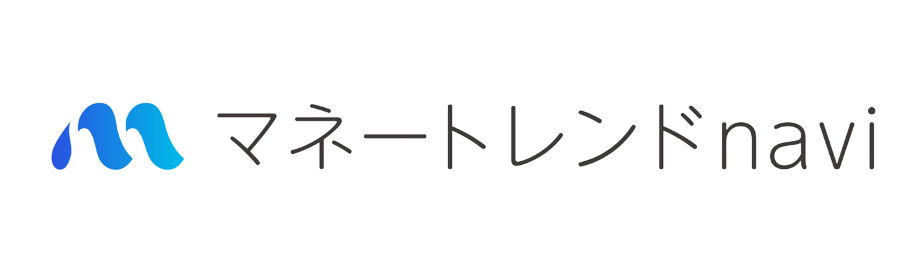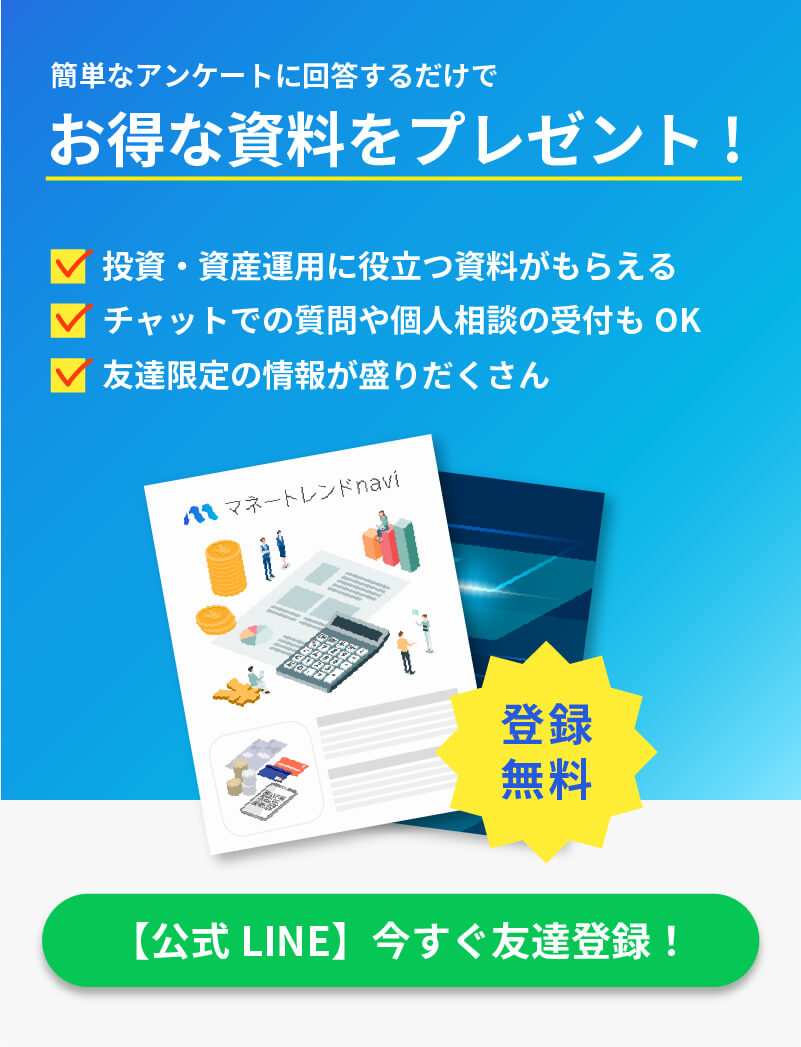多くの配当を受け取るには高配当利回りの銘柄に着目する必要があります。
配当が多い銘柄では、企業の株主への還元姿勢や高い収益性、成長度合いに期待可能です。
今回は、高配当利回りの30銘柄をランキング形式でまとめ、2023年2月17日現在の配当利回りや年間配当金を紹介しています。
また、各銘柄の本質を見極めるための指標や、高配当利回り銘柄の落とし穴なども解説しているので、投資前に一読いただけると幸いです。
記事の最後には株式投資以上の高利回りに期待できる「ファクタリング事業投資」についても紹介していますので、興味をお持ちの方はそちらもご覧ください。
配当利回りとは得られる配当を示す指標の一つ
配当利回りは、購入時点の株価に対する配当金の割合を示します。
各企業の株ごとに配当利回りは異なり、株の売買を判断するひとつの指標としてよく利用されます。配当利回りが高い銘柄は「高配当株」とも呼ばれ、高い配当を得られる可能性が高く、狙い目です。
配当利回りは以下の式で求められます。
【1株あたりの配当金÷購入時株価×100】
例:1株の年間配当金が20円で株価が4500円の場合、配当利回りは0.44%。
計算式:20円÷4,500円×100=0.44%
1株あたりの配当金が同じ株が2つあっても、株価が高いほうは配当利回りが低くなり、株価が高い方は配当利回りが低くなります。
配当利回りを活用すればよりお得に投資できる株を探せるので、投資指標の一つとして覚えておくと良いでしょう。
ちなみに配当利回りは「配当の予想」であり、配当金を保証する指標ではありません。あくまでも投資時の判断材料の一つとして活用することが大切です。
高配当利回りの定義は?利回りの平均はどのぐらい?
厳密な定義はありませんが、一般的には「4%」を超えていると高配当利回りの銘柄とされます。
しかし高配当利回りだからといってすぐに飛びつくようなことはせず、冷静に吟味することが重要です。
業績によって配当が減らされるリスクや、現在の利回りをキープする力がどれぐらいあるかといった複数の点を踏まえて投資先を判断しましょう。
ちなみに東証プライム市場(以前の東証一部)に上場している企業の2023年1月単純平均利回りは「2.23%」です。
市場や利回りの種類によって数値は変わりますが、2022年5月以降平均利回りは約2%〜2.5%程度の間で推移しています。
株の配当利回りは超低金利と呼ばれる銀行預金金利より高いことが多いので、資産を増やすための投資先にも向いています。
リスクヘッジを行ったうえで資産防衛・運用のために株への投資を検討するのも良いでしょう。
株式のように少ない手間で高い利回りを狙える投資として「ファクタリング事業投資」という方法もあります。
売掛債権を現金で買い取るファクタリング企業へ投資を行う「ファクタリング事業投資」では、12%〜18%といった利回りで資産運用できる可能性があります。
この数字は日本の高配当銘柄ランキングで上位にランクインする銘柄と同等程度なうえに、株式投資ではないことから株価変動リスクを避けることも可能です。
記事後半で詳細を解説するので、興味をお持ちの方はそちらもお読みください。
株式投資を行うときに注意すべきポイント
株式投資を行うときにはいくつか注意すべきポイントが存在します。
「株価が安いから」「配当利回りが良いから」「有名企業の銘柄だから」といった単純な理由だけで株を購入するのは早計です。
以下のポイントも意識し、よりリスクを抑えた投資を行えるようにしましょう。
- 「安い・高い」と「割安・割高」の違いを理解する
- 高配当銘柄だから必ず儲かるわけではない
- 投資先の企業について調べる
- 配当受取には権利付最終日までの買付が必要
「安い・高い」と「割安・割高」の違いを理解する
株式投資を行うときの1つ目のポイントは、「安い・高い」と「割安・割高」の違いを理解することです。
株式投資で利益を得るには「安いときに買い」「高いときに売る」ことが一般的な方法とされています。厳密には「割安時に買い」「割高時に売る」ことによってリスクを抑えた株式投資が可能です。
株価を「安い・高い」と判断する多くの人は、株購入時の買・売値や、価格をチェックしたタイミングの価格を「参照点」としている傾向にあります。
しかし、これらを参考にすると銘柄の適正価格を基準にした投資ができず、誤った売買判断をする可能性が高くなるのです。
投資理論の一つである「市場価格は適正価格に回帰する」という考え方を知ることで、割高状態の銘柄を安いと勘違いして売買するケースを減らすことができます。
自分の基準から「安い・高い」ではなく、適正価格より「割安・割高」かを見定めて、相場に逆らわない投資を行いましょう。
なお、銘柄の割安・割高を判断する指標である「PER」や「PBR」については後ほど紹介します。
高配当銘柄だから必ず儲かるわけではない
株式投資を行うときの2つ目のポイントは、高配当銘柄だから必ず儲かるとは思わないことです。
配当利回りは企業が業績予想に基づいて発表した配当金を使って求められた数字で、決して配当金を保証するものではありません。
万が一業績が悪ければ配当金は予想を下回り、受け取れる配当も少なくなります。
また、株価が下がると一時的に配当利回りが高くなりますが、価格下落の理由が業績悪化であれば配当金も引き下げられることが考えられます。
当初より配当金が引き下げられることを「減配」と呼び、ここ数年で売上が横ばいもしくは減少している企業は減配リスクを抱えているため注意が必要です。
企業業績が悪かったり、減配リスクがあるような銘柄は、例え配当利回りが高くても慎重に投資するようにしましょう。
配当受取には権利付最終日までの買付が必須
株式投資を行うときの3つ目のポイントは、配当を受け取るために権利付最終日までの買付を行うことです。
配当を受け取るには、権利付最終日までに必要な数だけ株を購入し、権利確定日までに企業の株主名簿に記載される必要があります。
権利付最終日は企業の決算期などによって変わるので、各社ホームページのIR情報ページで確認しましょう。
\ ここでお知らせ /
資産運用をしたい方必見!
インフレ時代を乗り切る強い味方とも言える「アンティークコインでの資産運用」について、
アンティークコインの魅力や市場価値・過去10年間の価格推移などについて詳しく解説しております。
株価や銘柄を評価する代表的な指標・指数
株価や銘柄を評価する代表的な指標・指数を紹介します。
資産の安全な投資先を選ぶには、銘柄を様々な視点から見て評価を下す必要があります。
これらの代表的な指標を覚えるだけでも、より聡明な売買判断ができるようになったり、お得に投資できるようになるので、ぜひ参考にしてください。
- 指標:配当性向
- 指標:株価収益率(PER)
- 指標:株価純資産倍率(PBR)
- 指標:1株あたり純利益(EPS)
- 指数:日経平均株価(日経225)
指標:配当性向
1つ目は、配当性向です。
配当性向は、企業が純利益からどのくらいの配当金を支払っているかを表します。配当性向が高ければ高いほど株主への還元率も高く、多くの配当を受け取れます。
しかし、配当性向の高低が企業の良し悪しを決めるわけではありません。
例えば、立ち上がったばかりで現在成長中の企業は利益を投資に回すことで事業を大きくするので、配当性向は低くなりがちです。
配当性向が高くても業績が悪い企業の銘柄を持っていると株価変動によって資産を失う可能性があります。
逆に成熟した企業は利益を株主へ還元することが多く、配当利回りも高くなるケースが見られます。
【配当性向の計算式】
配当性向=配当金支払い総額+当期純利益×100
指標:株価収益率(PER)
2つ目は、株価収益率です。
Price Earnings Ratioを略してPERと表記されるケースが多く、銘柄を評価するのに非常に役立つ指標となっています。
現在の株価が適正価格より割安か割高かを判断するのに利用でき、PER数値が低ければ割安、高ければ割高という評価を行います。
基本的には同業種の企業を比較したり、企業の過去のPERと現在のPERを照らし合わせて銘柄の価格感を判断するのが一般的な使い方です。
PERは業種によっても高低が分かれるため、同業種での比較に利用するのが好ましいとされています。
【PERの計算式】
PER=株価÷EPS(1株あたり純利益)
指標:株価純資産倍率(PBR)
3つ目は、株価純資産倍率です。
Price Book-value Ratioを略してPBRと呼ばれ、PERと同じく現在株価の割安・割高を判断します。
PBRの数値が高ければ割高、低ければ割安という判断を行います。
【PBRの計算式】
PBR=株価÷BPS(1株あたり純資産)
指標:1株あたり純利益(EPS)
4つ目は、1株あたり純利益です。
Earnings Per Shareを略してEPSと呼ばれ、企業の収益力を判断するのに利用されます。
この指標では、1株あたりでどのくらいの純利益を生み出しているかを判断でき、EPSが高いと今後株価の上昇に期待できます。
【EPSの計算式】
EPS=当期純利益÷発行済株式総数
指数:日経平均株価(日経225)
5つ目は日経平均株価です。
日経225とも呼ばれ、日本を代表する株価指数です。
東京プライム市場に上場している銘柄のなかからより流動性の高い225銘柄が選定され、225社の株価を元に算出されます。
対象となる225銘柄は年に1回見直されるため、採用銘柄の流動性の高さは常に保たれています。
株式投資に関する情報はどのように集める?
株式投資を行うには情報集めの質を高めることも重要です。
株に関する情報は主に以下の媒体から収集できるので、それぞれの特徴を理解して株式投資で活用できるようにしましょう。
- 四季報
- 証券会社のレポート
- ニュースサイト
- 経済新聞
四季報
四季報は日本国内企業の情報が掲載されている定番の株情報誌です。
基本的な会社情報から関連会社や財務データ、株価などが網羅されているため、株式市場のトレンドを掴むことができます。
発行は年に4回。現在はオンライン版もあるため、以前より扱いやすくなった点が嬉しいポイントです。
証券会社のレポート
証券会社や金融会社は定期的に相場レポートを発行します。
各社の口座開設や会員登録を行えば無料で閲覧できるものが多いため、しっかり活用できれば着実に相場知識を身につけられるでしょう。
プロのアナリスト目線で相場を見るきっかけにもなるので、いくつか気になった証券会社のレポートを読んでみるのもおすすめです。
ニュースサイト
ニュースサイトではリアルタイムの価格チャートや経済情報を確認できます。
他にも株価指数や投資に関する知識を学ぶコンテンツなども充実しているので投資学習にも役立ちます。
自分がより注目している銘柄をお気に入りに設定したりと、自分好みにサイトをカスタマイズできるものもあるため、投資環境を整えるのにも活用できます。
経済新聞
経済新聞は速報性こそネットニュースには劣るものの、それぞれの分野をより深堀りした内容が記載されているため、理解度を高めるのに役立ちます。
購読するには1ヶ月あたりの費用が発生しますが、独自の切り口から発信される情報も多く視野を広げるきっかけにもできるでしょう。
Twitterはどんな媒体よりも速報性に優れています。
要人発言や指標発表といった株価に直接影響を与える情報が素早く流れてくるため、売買判断に大きく活用できます。
しかし誰でも情報発信できることから、情報の真偽を自分で見極める力は必須です。
テレビや新聞といったメディアでも情報発信を行っている通信社の公式アカウントをメインに確認して、正しい情報を元に投資を行いましょう。
【2023年2月】高配当利回りの株式銘柄ランキングTOP30
2023年2月現在で高配当利回りを記録している30個の銘柄をランキング形式で紹介します。
株価や利回りは日々変動するため、あくまでも高配当を記録しやすい企業や業種を認識する参考としてご利用ください。
今回ランクインした全企業を列挙したあと、各社の配当利回り状況を解説していきます。
| 順位 | 会社名 | 業種 | 株価 | 配当利回り | PER | PBR |
| 1位 | 商船三井 | 海運 | 3,400 | 16.47% | 1.54 | 0.97 |
| 2位 | 日本郵船 | 海運 | 3,307 | 15.42% | 1.69 | 0.98 |
| 3位 | 川崎汽船 | 海運 | 3,305 | 12.10% | 1.45 | 1.06 |
| 4位 | NSユナイテッド海運 | 海運 | 4,075 | 8.71% | 3.62 | 0.83 |
| 5位 | 乾汽船 | 海運 | 2,041 | 8.67% | 5.61 | 1.78 |
| 6位 | 三井松島HD | 鉱業 | 3,825 | 8.37% | 2.38 | 1.41 |
| 7位 | ジャフコG | その他金融 | 2,130 | 7.04% | 78.05 | 0.79 |
| 8位 | 日本たばこ産業(JT) | 食品 | 2,759.5 | 6.81% | 12.54 | 1.56 |
| 9位 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 2,809 | 6.80% | 19.60 | 3.01 |
| 10位 | 石油資源 | 鉱業 | 4,860 | 6.79% | 4.40 | 0.71 |
| 11位 | 東芝 | 電気機器 | 4,353 | 6.66% | 18.85 | 1.56 |
| 12位 | 飯野海運 | 海運 | 953 | 6.51% | 4.76 | 1.14 |
| 13位 | 有沢製作所 | 化学工業 | 1,420 | 6.34% | 14.82 | 0.99 |
| 14位 | 西松建設 | 建設 | 3,505 | 6.31% | 19.88 | 1.29 |
| 15位 | 奥村組 | 建設 | 3,200 | 6.25% | 12.37 | 0.74 |
| 16位 | 三ツ星ベルト | ゴム | 3,855 | 6.23% | 18.48 | 1.45 |
| 17位 | ディア・ライフ | 不動産 | 619 | 6.14% | 6.78 | 1.33 |
| 18位 | 日本特殊陶業 | 窯業 | 2,731 | 6.08% | 6.56 | 1.08 |
| 19位 | タチエス | 自動車等 | 1,218 | 6.04% | 9.54 | 0.59 |
| 20位 | LA HD | 不動産 | 3,495 | 6.01% | 5.96 | 1.79 |
| 21位 | オプティマス | 商社 | 885 | 5.99% | 5.95 | 0.97 |
| 22位 | 大豊建設 | 建設 | 3,845 | 5.98% | 31.60 | 0.95 |
| 23位 | フージャース HD | 不動産 | 811 | 5.92% | 7.13 | 0.96 |
| 24位 | あかつき本社 | その他金融 | 321 | 5.92% | 18.21 | 0.78 |
| 25位 | 日本製鉄 | 鉄鋼業 | 3,049 | 5.90% | 4.32 | 0.84 |
| 26位 | 淺沼組 | 建設 | 3,245 | 5.89% | 12.73 | 1.24 |
| 27位 | ムトー精工 | その他製造業 | 1,052 | 5.85% | 7.40 | 0.60 |
| 28位 | あおぞら銀行 | 銀行 | 2,637 | 5.84% | 31.19 | 0.63 |
| 29位 | エーワン精密 | 機械 | 1,715 | 5.83% | 48.08 | 1.18 |
| 30位 | アーバネット | 不動産 | 309 | 5.83% | 7.18 | 0.76 |
1位:商船三井
日本の大手海運会社である商船三井は、コロナ後から大きく配当利回りを伸ばしています。
2021年3月は1株あたりの年間配当額が50円だったのに対し、2023年3月は560円と2年で約10倍という驚異の伸び率です。

2位:日本郵船
三菱グループの一つである日本郵船は、海上運送業や客船事業を行っています。
2021年3月から配当金が約7倍近く増えているうえに、4期連続増配が発表されたことと配当性向が約25%であることから今後の伸びにも期待可能です。

3位:川崎汽船
東京都の海運会社で、自動車専用船や液化天然ガス運搬船、ドライバルク船などで製品や資源を世界中に運送しています。
2022年3月期から復配し、2023年3月には2期連続増配と業績の良さが伺えます。

4位:NSユナイテッド海運
日本の準大手海運会社で、日本製鉄と日本郵船の関連会社です。
2021年3月から2023年3月までの2年間で約4倍近く配当が増加しています。

5位:乾汽船
海運業を中心に、不動産業や倉庫業を行っている会社です。
2021年3月の1株あたり配当額は6円だったのに対し2023年3月は177円と大きな伸びを見せています。
しかし、2022年3月から減配していることもあって投資には慎重になりたいところです。

6位:三井松島ホールディングス
福岡県の炭鉱事業業者で、エネルギーの供給に長きに渡って取り組んでいます。
2023年3月の1株あたり年間配当額は320円と、前年3月から4倍の数字となりました。

7位:ジャフコグループ
ジャフコグループは日本トップクラスのベンチャーキャピタルとして、さまざまな新興企業に出資を行っています。
2023年3月の1株あたり年間配当額は150円で、前年と比べると約3倍の伸びです。

8位:日本たばこ産業
日本たばこ産業はたばこだけじゃなく、医薬品や加工食品に関する事業も展開しています。
1株あたりの配当額は安定しており、直近の2023年12月は188円となっています。

9位:ドリームインキュベータ
ドリームインキュベーターは多くの企業に対してコンサルティングやプロデュースを行うことで事業サポート等を行っています。
しばらく無配状況が続いていましたが、2023年3月期に特別配当にて株主への還元が実施されることになりました。
総額100億円の株主還元計画は2025年6月まで続く予定です。

10位:石油資源開発
石油資源開発株式会社は、国内外で石油や天然ガスといった資源の生産や輸送などを行っています。
2023年3月期の年間配当額は330円と、3期連続50円だった状況から大きく抜け出しました。

11位:東芝
日本の中心的な電機メーカーである東芝は、エネルギーやインフラといった社会を支えるための幅広い事業を行っています。
2023年3月期の年間配当額は290円で、過去最高額となった2022年3月期の220円をさらに上回る数字を記録しています。

12位:飯野海運
飯野海運は海運業を中心に不動産業にも取り組んでいます。
3期連続増配となる2023年3月期の年間配当額は62円と、前年3月期の36円から大きく増加しています。

13位:有沢製作所
有沢製作所は新潟県のエレクトロニクス材料の開発や製造を行っている会社です。
レンズやプリント基板向けの材料を主力としてIT業界を支えています。
2021年3月期以前と比較すると年間配当額は増えていますが、前年3月と比べると5円減配の90円となっています。

14位:西松建設
西松建設は日本の準大手ゼネコンで、ダムやトンネルなどの建設・開発や不動産事業を行っています。
2023年3月の年間配当額は前年と同様の221円としています。

15位:奥村組
大坂に本社を置く奥村組は鉄道・ダムに関する土木工事やビル・住宅の建築工事などを行っています。
年間配当額は毎期安定している傾向にありますが、2023年3月は前年3月の172円から200円に上がるなど2期連続の増配となっています。

16位:三ツ星ベルト
三ツ星ベルトは、兵庫県神戸市に本社を置くゴムメーカーです。
自動車から産業機器に使用されるゴムや、電子機器に使用される導電性のある塗料などを取り扱っています。
2023年3月期の年間配当額は2021年3月の57円から約4倍近くの240円までに伸びています。

17位:ディア・ライフ
ディア・ライフは用地の取得から設計・建設、運営管理まで不動産全般に関する業務を一社で行っています。
不動産開発・投資の両方を手掛けた効率的な経営が特徴です。
2023年3月期の年間配当額は38円と、前年3月期の44円より減配という形となっています。

18位:日本特殊陶業
日本特殊陶業は、エンジン内部でライターの役割を果たす「スパークプラグ」やセラミックス素材を生かした医療関連製品などを製造しています。
年間配当額が102円だった2022年3月期に対し、2023年3月期は166円に増配しています。

19位:タチエス
タチエスは日本でも少ない自動車のシートを製造する会社です。
元々属していた日産や日野自動車を中心に取引を行っています。
2021年3月期は6.5円の年間配当額でしたが、2023年3月期は73.6円と連続増配となっています。

20位:LAホールディングス
LAホールディングスはラ・アトレの株式移転によって2020年7月に設立されました。
新築不動産の販売や、賃貸事業などを中心にグループ会社の経営管理などを行っています。
連続増配によって2023年12月の年間配当額は210円と、3年前と比べて約5倍近くになっています。

21位:オプティマス
オプティマスグループでは中古自動車を日本から海外へ輸出し、さらにはそれに付随した事業をニュージーランドを中心に行っています。
2023年3月期の年間配当額は53円と前年3月期の46円から微増ではあるものの連続増配となっています。

22位:大豊建設
大豊建設は東京に本社を置く建設会社で、土木建築工事の請負からコンサルティング、不動産関連事業など幅広い業務を行っています。
2023年3月期の年間配当額は前年3月期の243円から13円減の230円となっています。

23位:フージャースホールディングス
フージャースホールディングスは全国で新築分譲マンション事業や、シニア向け新築マンション事業などを行うグループ会社の経営管理などを行っています。
2023年3月期の年間配当額は48円と、前年3月期の36円から連続増配となりました。

24位:あかつき本社
あかつき本社は証券や不動産を取り扱うグループ企業の統括企業です。
ここ数年で年間配当額に大きな変化はありませんが、2023年3月期は前年3月より1円高い19円に増配した形となっています。

25位:日本製鉄
日本の鉄鋼メーカーとして最大手である日本製鉄は、製鉄事業を中心に産業界を支える事業を広く展開しています。
2022年3月期には160円、2023年3月期には180円と連続増配となっています。

26位:淺沼組
淺沼組は大阪府に本社を置くゼネコンで、官公庁建設から道路、鉄道、空港や上下水道の設計・管理など幅広く街づくりに関わっています。
5期連続増配によって2023年の年間配当額は191円となっています。

27位:ムトー精工
ムトー精工はプラスチック部品の金型設計・製作・加工・組立を行っており、ソニーやデンソー、パナソニックといった多くの電気メーカーと取引しています。
2023年3月期の年間配当額は61.5円と前年3月期から3倍近く増配しています。

28位:あおぞら銀行
国内外に営業拠点がある銀行で、ユニークで存在感が強い銀行を目標としています。
年間配当額は毎期安定しており、2023年3月は154円と連続増配となっています。

29位:エーワン精密
精密加工用マシンで使用される工具に関する事業を行っているエーワン精密。
既存品の製造から新たな工具の製造まで、非常に広いニーズに対応しています。
2023年3月期の年間配当額は100円と前年3月期から横ばいです。

30位:アーバネット
アーバネットは自社マンション事業と都市開発事業を行っており、美しさと利便性を兼ね備えたマンションの展開が特徴です。
2019年6月期以降の年間配当額は17円から20円を推移しており、安定した配当に期待できます。

高利回りの投資ならファクタリング事業投資もおすすめ
配当利回りが高い投資を行うなら、ファクタリング事業投資もおすすめです。
ファクタリングとは企業の売掛債権を現金で買い取るサービスです。
資金難の企業がファクタリング事業を行う企業に売掛債権を売却し現金を得ることで、キャッシュフローの改善が見込めます。
ファクタリング企業は売掛債権分から手数料を引いた金額で購入できるため、売掛先から現金が回収できれば手数料分が利益となります。
高利回りで投資できるのが特徴
ファクタリング事業投資では、売掛債権を買い取る側である「ファクタリング企業」に投資を行います。
最大の特徴は国債や社債を大きく超える可能性のある高い利回りで、ケースによっては12%〜18%ほどで運用可能です。
ファクタリング企業は売掛先の信用調査を徹底しているうえに、複数社の売掛債権によるポートフォリオを形成しているため、損失を他の利益でカバーできます。
このように、リスクを抑えつつ高利回りの投資を実現できる点がファクタリング事業投資のメリットといえるでしょう。
当社で取り扱うファクタリング事業投資では徹底的なリスク管理によって安定した利益の確保と還元に力を入れています。
財務コンサルティング提供によって内部を熟知した企業に対してファクタリングを実施することでローリスクな資金調達支援・運用と積極的な事業提供が可能です。
不動産や建築、ITや広告といった幅広い分野の企業と連携密度の濃い取引を行っていることで年間売上規模は50億円を超え、投資家の皆様にも高配当に期待いただけます。
事業内容をもう少し深く知りたい方はマネートレンドnaviの公式LINEを追加いただき、直接お問い合わせください。
下記記事でファクタリング事業投資について解説も行っているので、公式LINEと共に情報取得に役立てていただけますと幸いです。
高配当利回り銘柄でも慎重に!企業の実態を見極めて投資しよう
今回は高配当利回りの銘柄ランキングを中心に、高配当の定義やそれらを見極める指標について紹介しました。
株価変動や企業動向は予想が難しく、どれだけ安全とされている銘柄であっても価格が暴落するリスクを抱えています。
株価が下がれば配当も減配となる可能性が考えられるため、配当を目的とした株式投資時には企業の実態を見極めて投資先の選択を進めましょう。
また、高配当利回りランキング上位の銘柄だからといって必ず儲かるわけではありません。
配当を受け取るには一定期間株を保有し続ける必要があり、その間に価格変動によって含み損を抱える可能性も考えられます。
割安・割高のように適正価格を水準とした売買判断や各指標を活用した客観的な視点での銘柄選びでリスクを抑えた投資を行えるようにしてください。
高配当が期待できる投資として、当社が提供するファクタリング事業投資もおすすめです。
ファクタリング事業投資では、当記事で紹介したランキング上位銘柄と並ぶ、もしくは上回る高配当も期待できます。また、信用情報の精査や分散投資によるリスク軽減の取り組みも強みのひとつです。
ファクタリング事業投資の詳細資料は公式LINEにてお配りしているので、興味のある方はぜひ友達登録のうえ、チャットからお問合せください。